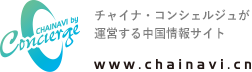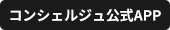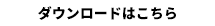- ビジネス記事
PERSOLKELLY Consulting
コンプライアンス規程の整備について
今号では香港におけるコンプライアンス規程の整備ポイントについてご案内いたします。
昨今、日本ではコンプライアンスという用語が広く使われておりますが、香港においてもコンプライアンス遵守の重要性は年々高まっております。
コンプライアンスとは、法令遵守という考え方だけではなく、社内規則の遵守、さらには倫理観をもった行動により社会秩序の維持や社会的責任を果たすことも含まれるという考え方もあります。コンプライアンスを心がけることは、企業にとっては事業の存続やブランド価値の維持、向上に繋がります。
関連法令について
人事・労務領域におけるコンプライアンス規程の整備については、香港では雇用条例(日本の労働基準法に相当)以外にも留意すべき関連条例として、差別条例、個人情報保護条例、賄賂防止条例、競争条例、MPF条例、最低賃金条例があります。いずれも法律を知らなかったり良く理解できていなかったがゆえにトラブルとなってしまうケースが多くあります。具体例として、今号では差別条例について、その概要と会社側の義務・対策についてご紹介したいと思います。
差別条例について
香港では現在4つの差別条例があります。各種差別条例における差別禁止項目は次の通りです。
①性的差別条例…性別・婚姻状況・妊娠
②障害者差別条例…障害(健康状態なども含む)
③家族状況差別条例…家族状況(同居家族の特殊な事情など)
④人種差別条例…人種(人種・皮膚の色・世系・民族的出身・種族的出身を含む)
監督官庁の機会均等委員会(以下、EOC[Equal Opportunities Commission])は、各種差別に対する調査権および執行権を持ち、差別防止のために活動を続けています。被害者から訴えがあった場合にEOCは調査や調停を行いますが、状況によっては被害者に対し裁判所に訴えを起こすよう勧め、法的支援を提供することもあります。
会社側の義務と対策
では、会社側にはどのような義務があり、またどのような対策が必要か見ていきたいと思います。まずトラブルを未然に防ぐために、「差別撤廃に対する方針」を定め、社員への周知・日常のマネジメントへの落としこみをしていくことが肝要です。
雇用期間に労働者による差別や嫌がらせがあった場合、会社側は労働者が行った差別行為に対し代理責任を問われる可能性があります。代理責任を問う訴えを起こされた場合、会社側が差別撤廃のためにどのような努力を行ったかが裁定に影響してきます。差別撤廃に対する方針を明確にしていれば、「合理的な手段」をとっていたと見なされることがあるため、就業規則などで方針を明記する、内部通報制度を設ける、講習会を開催するといったことが対策として挙げられます。自社内でどれだけ周知徹底の仕組みづくりができているか、一度点検することをお勧めいたします。
コンプライアンス規程の整備
ここまで差別条例についてご紹介をさせて頂きましたが、個人情報保護条例、賄賂防止条例、競争条例等につきましても同様に対策が必要となります。
昨今、日本ではコンプライアンスという用語が広く使われておりますが、香港においてもコンプライアンス遵守の重要性は年々高まっております。
コンプライアンスとは、法令遵守という考え方だけではなく、社内規則の遵守、さらには倫理観をもった行動により社会秩序の維持や社会的責任を果たすことも含まれるという考え方もあります。コンプライアンスを心がけることは、企業にとっては事業の存続やブランド価値の維持、向上に繋がります。
関連法令について
人事・労務領域におけるコンプライアンス規程の整備については、香港では雇用条例(日本の労働基準法に相当)以外にも留意すべき関連条例として、差別条例、個人情報保護条例、賄賂防止条例、競争条例、MPF条例、最低賃金条例があります。いずれも法律を知らなかったり良く理解できていなかったがゆえにトラブルとなってしまうケースが多くあります。具体例として、今号では差別条例について、その概要と会社側の義務・対策についてご紹介したいと思います。
差別条例について
香港では現在4つの差別条例があります。各種差別条例における差別禁止項目は次の通りです。
①性的差別条例…性別・婚姻状況・妊娠
②障害者差別条例…障害(健康状態なども含む)
③家族状況差別条例…家族状況(同居家族の特殊な事情など)
④人種差別条例…人種(人種・皮膚の色・世系・民族的出身・種族的出身を含む)
監督官庁の機会均等委員会(以下、EOC[Equal Opportunities Commission])は、各種差別に対する調査権および執行権を持ち、差別防止のために活動を続けています。被害者から訴えがあった場合にEOCは調査や調停を行いますが、状況によっては被害者に対し裁判所に訴えを起こすよう勧め、法的支援を提供することもあります。
会社側の義務と対策
では、会社側にはどのような義務があり、またどのような対策が必要か見ていきたいと思います。まずトラブルを未然に防ぐために、「差別撤廃に対する方針」を定め、社員への周知・日常のマネジメントへの落としこみをしていくことが肝要です。
雇用期間に労働者による差別や嫌がらせがあった場合、会社側は労働者が行った差別行為に対し代理責任を問われる可能性があります。代理責任を問う訴えを起こされた場合、会社側が差別撤廃のためにどのような努力を行ったかが裁定に影響してきます。差別撤廃に対する方針を明確にしていれば、「合理的な手段」をとっていたと見なされることがあるため、就業規則などで方針を明記する、内部通報制度を設ける、講習会を開催するといったことが対策として挙げられます。自社内でどれだけ周知徹底の仕組みづくりができているか、一度点検することをお勧めいたします。
コンプライアンス規程の整備
ここまで差別条例についてご紹介をさせて頂きましたが、個人情報保護条例、賄賂防止条例、競争条例等につきましても同様に対策が必要となります。
ルールや仕組みを構築、導入するだけではなく、これらが適切に運用され、かつ有効に機能するように、実際に活動する社員一人ひとりがコンプライアンスの重要性を理解し、実行動につなげられるよう働きかけることが重要となります。