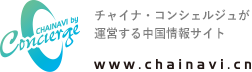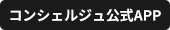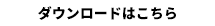中国の法律

- ビジネス記事
- 中国の法律
北京中諮律師事務所
中国特許法の手引き(13)
前回までは特許出願、特許審査、特許無効宣告など、特許にかかわる手続について説明いたしました。
今回は発明特許権の帰属に関する概要および共同発明による特許権の帰属についてご説明します。
① 概説
ある発明が完成されてから特許出願を提出するまでには、法律的な意味における帰属の問題が存在します。特許法においては、基本的に以下の3つの点を明確にする必要があります。
①誰が特許の出願権利を持つのかについて
②特許出願が提出された後、権利付与がされる前の、いわゆる「特許出願権(原文は「専利申請権」)」の行使について
③特許出願が権利を取得した後の、当該特許権の帰属について
② 共同発明の構成要件
中国の「特許法」第8条には、協力して完成させた発明について、約定のない場合には、完成に協力した者は共同発明者となると規定されています。ある発明が共同発明であるかどうかを判断するには、発明者の間に「協力」が存在するか否か、および協力者が「創造的な貢献」をしたかどうかがキーポイントとなります。これらのいずれの要素が欠けてもいけないのです。
発明者の間の法律上の意味における協力には、関連主体による合意も含まれます。合意とは、双方が共同発明者となる主観的な意思を有していることを指します。また、共同発明者の間には最低限の協力が存在しなければなりません。協力者の創造的な貢献に関する要求は、「特許法実施細則」第13条の「発明者」に対する要求、すなわち「特許法にいう発明者または創作者とは、発明創造の実質的な特徴に対して創造的な貢献をした者をいう」からきています。この要求は共同発明者にも適用されています。しかしながら、「創造的な貢献」の判断基準について正確に定義することは大変難しいと言えます。理論上、発明者は発明の構想に対して創造的な貢献をしていなければならず、発明の構想は通常、特許請求項で画定される技術案で具現化されています。
③ 共有特許権の行使
中国の「特許法」第15条には、「特許出願権または特許権の共有者は、権利の行使について約定のある場合は、その約定に従う。約定のない場合は、共有者は、当該特許を単独で実施し、または通常実施許諾の方式で他人に実施を許諾することができる。当該特許の実施を他人に許諾したとき、受け取った使用料は、共有者間で分配しなければならない」と規定されています。
中国の特許法の下では、約定のない場合、共有者は対外的に通常実施許諾を付与することができますが、他の共有者に許諾料の収益を分配しなければなりません。
④ 共有特許権の権益の処分
中国の民法においては、共有は持分共有(原文は「按份共有」)と共同共有(原文も「共同共有」)に分かれており、さらに共有者が共有権益を処分するために様々な法的規律が規定されました。しかしながら、特許法第15条が公布されるまでは、特許共有にかかわる性質を規定する法律はなく、理論上において大きな意見の相違がありました。そして現在第15条の規定があるとはいえ、この論争は終結したわけではありません。本条は特許権の共有の性質について明確に規定しているわけではないため、特許権の共有に関して持分共有の規律が適用されるのか、または共同共有の規律が適用されるのかが分からない状況です。この問題はさらに立法を行うことで明確にすることが求められます。
合わせてチェックしたい!
-

ビジネス記事中国の法律
- 北京市安理律師事務所
- 職場におけるAI活用の法的 リスクとコンプライアンス管理の枠組み
-

ビジネス記事中国の法律
- 北京市安理律師事務所
- 中国外資系企業による 反制裁法対応のコンプライアンスガイダンス
-

ビジネス記事中国の法律
- 北京市安理律師事務所
- 新会社法における 役員賠償責任保険の変化と分析
-

ビジネス記事中国の法律
- 北京市安理律師事務所
- 『弾力的定年退職制度実施暫定弁法』の 要点と実務への影響の分析
-

ビジネス記事中国の法律
- 北京市安理律師事務所
- 外資による中国国内の不良資産投資への 参加機会とスキームに関する検討
-

ビジネス記事中国の法律
- 北京市安理律師事務所
- 民事事件における「案由」選択の ジレンマからの脱出口 — 予備的請求